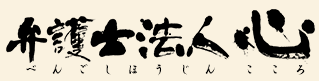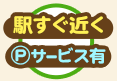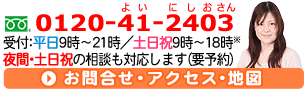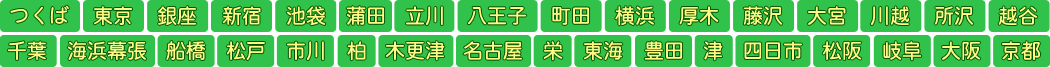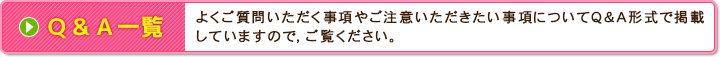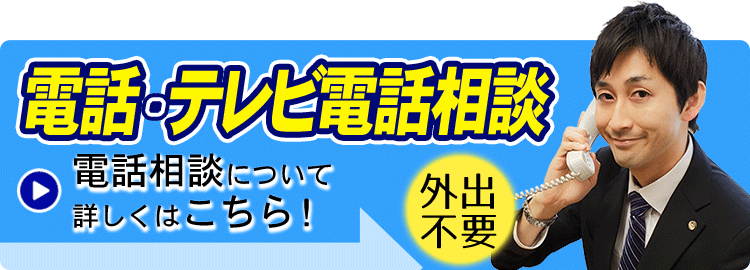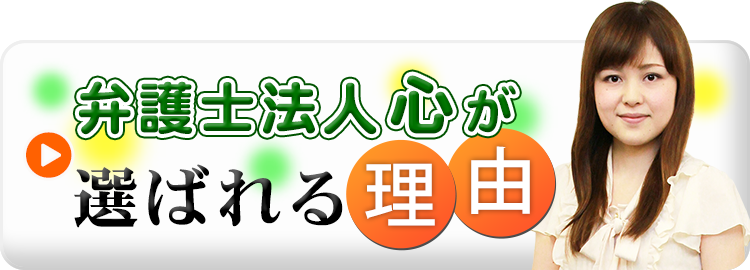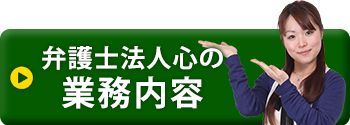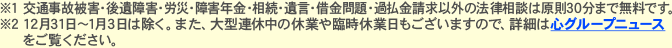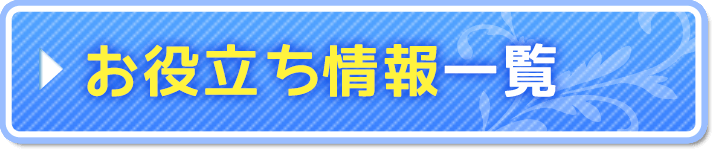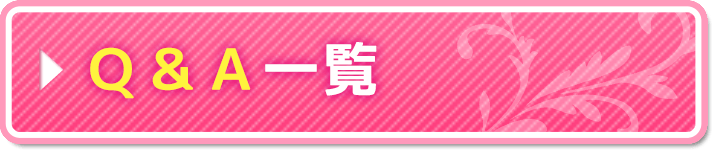地主の相続対策|不動産相続を円滑にするために
多くの不動産を代々受け継いで所有している地主の方が亡くなった場合には、不動産の相続をめぐってトラブルが生じる可能性が高くなります。
また、不動産の評価額によっては、高額な相続税が課税されるリスクもありますので、多数の不動産を所有している地主の方は、早めに相続対策に着手する必要があります。
元気なうちからしっかりと相続対策を行っておくことによって、将来のトラブルを回避することができるだけでなく、残された相続人の負担も軽減することができるため、円満な相続を実現することが可能になります。
今回は、地主の相続における相続対策について解説します。
1 地主の相続で発生するトラブル例
不動産を多数所有する地主の方が亡くなった場合には、以下のようなトラブルが生じる可能性があります。
⑴ 相続人同士のトラブルが生じやすい
被相続人が死亡した場合には、被相続人の遺産の分割方法について、相続人全員で話し合いをして決めていく必要があります。
現金や預貯金であれば、単純に相続人の法定相続分で分割すれば良いですが、不動産の場合には、物理的に分割することができない性質の財産であるため、その分割方法をめぐって相続人同士でトラブルが生じる可能性があります。
たとえば、相続人の一人が不動産を相続し、その代償として他の相続人に金銭を支払うという「代償分割」を選択する場合には、不動産の評価方法でトラブルが生じやすくなります。
不動産を相続する予定の相続人としては、自分が支払う代償金をできる限り少なくしたいと考えるため、不動産の評価を低く算定しようとします。
他方、代償金をもらう立場の相続人としては、できる限り多くの代償金をもらいたいと考えるため、不動産の評価を高く算定しようとします。
このような相続人同士の対立生じた場合には、話し合いでの解決は難しく、場合よっては遺産分割調停や遺産分割審判によって解決しなければならないこともあります。
このように不動産が遺産に含まれる場合には、不動産特有の難しさがありますので、相続人同士でトラブルが生じ、遺産分割が長期化する傾向にあります。
⑵ 高額な相続税が課税される可能性
相続が発生したからといって、常に相続税が発生するというわけではありません。
相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告や納税は不要です。
相続税の基礎控除額の計算は、以下のような計算式によって行います。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
たとえば、法定相続人が配偶者、長男、長女の3人であった場合には、相続財産の合計額が4800万円(3000万円+(600万円×3)=4800万円)までであれば、相続税は非課税となります。
しかし、地主の方の場合には、多数の不動産を所有していますので、相続財産の総額も高額になる傾向があります。
相続税の基礎控除を大幅にオーバーする相続財産を有していることもありますので、その場合には、高額な相続税が課税されるリスクがあります。
⑶ 活用していない不動産は相続人の負担になる可能性
多数の不動産を所有していたとしても、そのすべてに価値があるというわけではありません。
広大な山林を所有していたとしても、相続人にとっては利用価値がなく、毎年、固定資産税の支払いをしなければならないという負担が生じます。
また、老朽化した空き家を相続したとしても、取り壊すために何百万円もの費用を負担する余裕がなく、定期的な管理の負担だけを負わされるということもあります。
このように、不動産といってもさまざまな種類があり、不動産の状態によっては、相続人にとって多大な負担が生じるということもあります。
2 地主の相続対策
相続財産に不動産が含まれる場合には、上記のようなトラブルが生じるリスクがありますので、地主の方としては、早めの相続対策が重要となります。
生前にできる相続対策としては、以下のものが考えられます。
⑴ 遺言書の作成
相続財産をめぐる相続人同士のトラブルを防止するために有効なのが遺言書の作成です。
遺言書が存在しなければ、被相続人の遺産は、相続人による遺産分割協議によってその分割方法を決めなければなりません。
遺産分割協議では、相続人それぞれの思惑があり、それぞれが自分に有利に進めようとする結果、相続人同士でのトラブルが生じることになります。
しかし、あらかじめ遺言書を残しておくことによって、遺言者の希望通りの遺産分割方法を実現することができ、それによって、相続人の負担やトラブルを回避することが可能になります。
もっとも、相続人には、最低限度の遺産の取り分である「遺留分」が民法上保障されていますので、遺留分を侵害するような内容の遺言書であった場合には、遺留分をめぐる争いに相続人が巻き込まれてしまう可能性があります。
そのため、遺言書を作成する場合には、相続人の遺留分に配慮した内容で作成する必要があります。
また、遺言書の形式や内容に不備があった場合には、やはり遺言書の有効性をめぐって相続人でトラブルが生じる可能性もあります。
遺言書の作成をする際には、専門家である弁護士に相談をして不備のない遺言書を作成することが重要となります。
⑵ 節税対策
相続税の基礎控除額をオーバーする財産を有している場合には、相続税の負担を減らすための節税対策をする必要があります。
相続税は、相続財産の評価額に応じて負担しなければなりませんので、相続財産の評価額を減らすことによって相続税の節税につながります。
また、生前贈与などによって相続財産自体を減らす方法や、法律上の軽減措置を利用するということも有効な手段となります。
節税対策としてどのような方法が最適なのかについては、相続財産の総額、所有している不動産の状況などによって異なってきます。
そのため、税理士などの専門家に相談をしながら最適な節税対策を検討していくとよいでしょう。
⑶ 納税資金の確保
相続税の基礎控除額をオーバーする場合には、遺産を相続した相続人が相続財産の金額に応じた相続税を納めなければなりません。
「地主の相続人であれば、高額な相続税でも遺産から払えるのでは?」と思う方も多いかもしれません。
しかし、地主の方の資産は、そのほとんどが不動産によって構成されており、現金や預貯金は多くないということがあります。
相続税は、現金での支払いが原則となりますので、相続財産自体は多かったとしても、支払いに充てることのできる現金がなく、相続税が支払えないという事態になることも少なくありません。
そのため、相続人に相続税の納税の負担が生じることが予想される場合には、不動産の一部を売却することや相続人を受取人とする生命保険に加入するなどして、納税資金確保のための対策を講じる必要があります。
⑷ 不要な不動産はあらかじめ処分・活用しておく
現在活用していない不動産がある場合には、そのままの状態で相続人に引き継いだとしても相続人にとっては負担にしかなりません。
利活用の見込のない不動産については、あらかじめ処分しておけば、老後の生活資金や納税資金として利用することも可能です。
また、更地にアパートやマンションを建てることで、相続財産の評価を下げることもできます。
このように、不要な不動産については、あらかじめ処分・活用しておくことによって、相続人の負担を少しでも減らすことが可能になります。
ご自身が高齢になり、判断能力が低下してきてからでは、有効に不動産を利活用することができませんので、元気なうちから少しずつ対策を講じていくことが重要になります。
3 不動産が絡む相続対策は弁護士へ
相続対策の基本となる遺言書の作成は、法律問題の専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士は、あらゆる法律問題を取り扱っていますので、相続でどのような争いが生じるのか、争いが生じないようにするためにはどのようにしたらよいかなどについて豊富な知識やノウハウを有しています。
相続対策は、将来の相続人同士の争いを防止する観点から行うものですので、専門家である弁護士によるサポートを受けることによって、有効な対策を講じることができます。
形式的に問題のない遺言書の作成ができることはもちろんのこと、相続人の遺留分にも配慮した内容で遺言書を作成してもらうことができます。
遺言内容を実現するための遺言執行者を弁護士に依頼をするということも、相続対策としては有効です。
不動産を多数所有している地主の方は、将来の相続トラブルを回避するためにも、弁護士に相談をして相続対策のサポートをしてもらうことをおすすめします。
誹謗中傷と正当な批判の違い|表現の自由で保障される言論の範囲 賃貸借契約に係る賃料の供託|賃貸人が負う供託のリスクと対処法