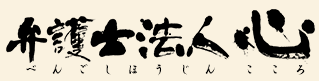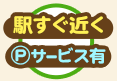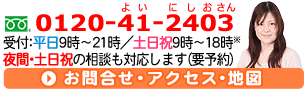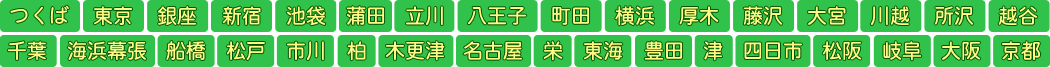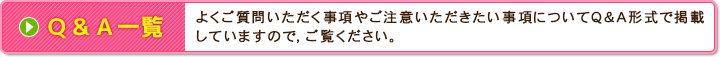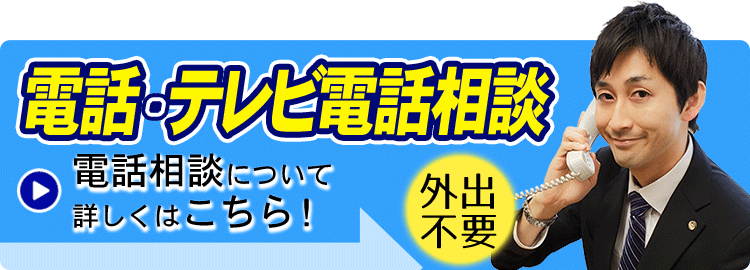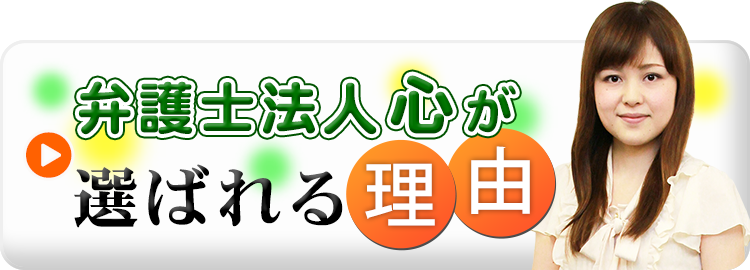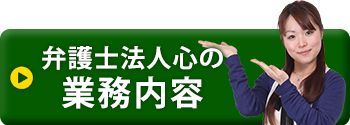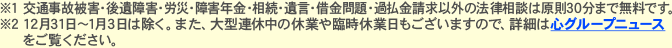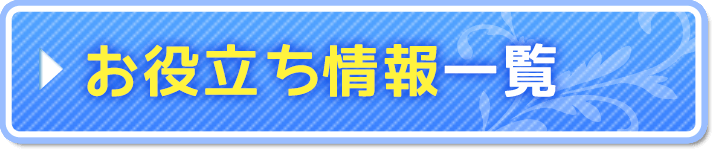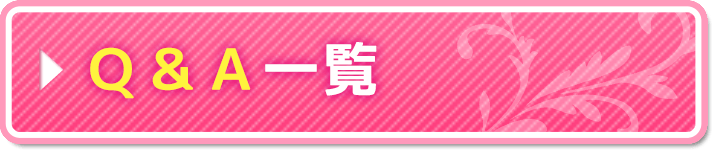誹謗中傷と正当な批判の違い|表現の自由で保障される言論の範囲
インターネット上の誹謗中傷は、被害者の心に大きな傷を与える許しがたい行為です。
その一方で、日本国憲法では表現の自由が保障されており、違法な誹謗中傷と正当な批判の境目が曖昧になるケースもあります。
インターネット上の投稿が違法であるか適法であるかは、刑法上の犯罪に当たるかどうか、民法上の不法行為に当たるかどうかという基準によって判断されます。
今回は、誹謗中傷と正当な批判の違いにつき、表現の具体例を交えながら解説します。
1 誹謗中傷と表現の自由の関係性について
日本国憲法では、言論を含む表現の自由が保障されています(日本国憲法21条1項)。
インターネット上の投稿も、表現の自由によって保障される言論の一つです。
その一方で、インターネット上で誹謗中傷の投稿が行われると、その内容を見て傷ついたり、信用面で悪影響を受けたりするという被害が発生することがあります。
誹謗中傷の投稿による被害を受けた方にも、人格権・名誉権・プライバシー権など(日本国憲法13条)が保障されています。
誹謗中傷の投稿は、こうした被害者の人格権などを侵害するものと捉えることもできるでしょう。
上記のように、表現の自由と人格権・名誉権・プライバシー権などは、時に対立する場面が生じ得ます。
この場合、「公共の福祉」によって、対立する権利の間で調整が図られることになります(日本国憲法13条)。
「公共の福祉」とは、他人の人権を侵害するような自由や権利を制限する原理です。
例えば、インターネット上の投稿が不当な誹謗中傷であれば、被害者の人格権・名誉権・プライバシー権を保護するため、投稿者の表現の自由が制限されます。
具体的には、被害者の人権を侵害するような投稿を強制的に削除するなどの対応がとられます。
反対に、インターネット上の投稿が正当な批判であれば、投稿者の表現の自由を保護するため、被害者の人格権・名誉権・プライバシー権が制限されます。
具体的には、投稿がインターネット上に公開されていることについて、被害者に我慢してもらうということです。
投稿者の表現の自由と、批判等の対象者の人格権・名誉権・プライバシー権のどちらを優先すべきかについては、投稿に用いられた表現の必要性や相当性などを考慮して判断されます。
その判断基準は、刑法や民法などにおいて具体化されています。
2 違法な誹謗中傷の要件・誹謗中傷表現の具体例
違法な誹謗中傷と正当な批判の境目を判断する基準として、もっとも重要なのは「犯罪に当たるかどうか」という点です。
以下では、誹謗中傷を行った場合に成立する可能性のある犯罪について、成立要件と表現の具体例を解説します。
⑴ 名誉毀損罪の要件・表現の具体例
名誉毀損罪(刑法230条1項)は、以下の要件をすべて満たす場合に成立します。
<名誉毀損罪の成立要件>
- ① 公然と発言(投稿)がなされたこと
- ② 発言(投稿)において、何らかの事実が摘示されたこと
- ③ 発言(投稿)が他人の社会的評価を下げる性質のものであること
- ④ 「公共の利害に関する場合の特例」の要件を満たさないこと
<名誉毀損罪の表現例>
- ・Aは不倫をしているので、社会的制裁を受けるべきだ。
- ・Bは学歴詐称をしているため、上場企業の役員にはふさわしくない。
名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
なお、2025年6月1日からは懲役と禁固が一本化され拘禁刑となります。
⑵ 侮辱罪の要件・表現の具体例
侮辱罪(刑法231条)は、以下の要件をすべて満たす場合に成立します。
<侮辱罪の成立要件>
- ① 公然と発言(投稿)がなされたこと
- ② 発言(投稿)が他人の社会的評価を下げる性質のものであること
- ③ 発言(投稿)において、事実の摘示がないこと(事実の摘示がある場合には、名誉毀損罪が成立)
<侮辱罪の表現例>
- ・Aはバカだ。
- ・Bは不細工だ。
侮辱罪の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
事実の摘示がない分、名誉に対する侵害の程度が小さいと考えられるため、名誉毀損罪よりも軽い法定刑が設定されています。
⑶ 偽計業務妨害罪の要件・表現の具体例
偽計業務妨害罪(刑法233条)は、以下の要件をすべて満たす場合に成立します。
<偽計業務妨害罪の成立要件>
- ① 偽計を用いたこと(他人を騙し、または他人の錯誤もしくは不知を利用したこと)
- ② ①により、他人の業務を妨害したこと
<偽計業務妨害罪の表現例>
飲食店Xは、原材料の産地を偽装しているので行かない方がよい(実際には、産地偽装の事実はない)
偽計業務妨害罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
⑷ 威力業務妨害罪の要件・表現の具体例
威力業務妨害罪(刑法234条)は、以下の要件をすべて満たす場合に成立します。
<威力業務妨害罪の成立要件>
- ① 威力(他人の自由意思を制圧するに足る勢力)を用いたこと
- ② ①により、他人の業務を妨害したこと
<威力業務妨害罪の表現例>
飲食店Yに爆弾を仕掛けたので、爆発に巻き込まれたくなければ行かない方がよい。
威力業務妨害罪の法定刑は、偽計業務妨害罪と同じく「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
⑸ 違法な誹謗中傷には不法行為も成立
上記の各犯罪に該当する誹謗中傷の投稿は、被害者に対する不法行為にも当たります(民法709条)。
誹謗中傷の被害者は、投稿者(加害者)に対して損害賠償を請求できるほか、裁判所に対して、投稿者に対する名誉回復措置命令を請求することも可能です(民法723条)。
3 違法な誹謗中傷に当たらない「正当な批判」とは
他人に対する批判的な内容の投稿であっても、「公共の利害に関する場合の特例」の要件を満たす場合には、違法性のない正当な批判として取り扱われます。
また、何らかの事実を前提とした意見や論評についても、公共の利害に関する場合の特例に準じて違法性が阻却(否定)され、正当な批判として取り扱われる場合があります。
⑴ 「公共の利害に関する場合の特例」の要件を満たす場合
以下の3要件を満たす言動(投稿)については、公共の利害に関する場合の特例に基づいて違法性が阻却され、名誉毀損罪が不成立となります(刑法230条の2第1項)。
<公共の利害に関する場合の特例の要件>
- ① 言動が公共の利害に関する事実に関係すること
- ② 言動の目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- ③ 摘示された事実が真実であることの証明があったこと
なお、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実に係る言動の場合、上記のうち③の真実性の証明があれば、それだけで名誉毀損罪としての違法性が阻却されます(同条3項)。
⑵ 他人を批判する意見や論評の違法性阻却について
何らかの事実を基礎として行われる意見や論評については、以下の3要件を満たすことを条件として、違法性が阻却されます(最高裁平成9年9月9日判決)。
- ① 言動が公共の利害に関する事実に関係すること
- ② 言動の目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- ③ 論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったこと
- ④ 人身攻撃に及ぶなど、意見・論評としての域を逸脱したものでないこと
⑶ 違法性のない正当な批判表現の具体例
公共の利害に関する場合の特例や、意見・論評の違法性阻却要件に鑑み、違法性のない正当な批判の表現例は、以下のとおりです。
<違法性のない正当な批判の表現例>
- ・政治家Aは、X社から賄賂を受け取っている。(賄賂授受が真実であることの証明があった場合)
- ・(芸能人Bが刑事事件の被疑者として取調べを受けているという事実を前提に)Bが出演しているテレビ番組を放送すべきでない。
スポンサーにとってのイメージダウンに繋がり、デメリットが大きいからだ。(芸能人Bが刑事事件の被疑者として取調べを受けているという事実が、重要な部分について真実であることの証明があった場合)
4 誹謗中傷の被害を受けた場合の対処法
インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた場合、被害者がとり得る対処法としては、以下のものが挙げられます。
- ・投稿の削除を申請する
- ・匿名投稿者を特定する
- ・投稿者を刑事告訴する
- ・投稿者に対して損害賠償を請求する
問題となる投稿が違法な誹謗中傷ではなく、正当な批判である場合には、上記の各対応は認められない可能性が高いです。
しかし、違法な誹謗中傷と正当な批判の境目は曖昧であり、判断が難しいケースも少なくありません。
投稿が違法である理由や、具体的な損害額などを法的・論理的に主張できれば、被害者の主張が認められる可能性は大いにあります。
インターネット上の誹謗中傷被害は、お早めに弁護士までご相談ください。
民事再生をお考えの方へ 地主の相続対策|不動産相続を円滑にするために