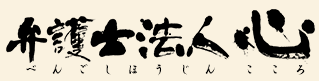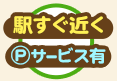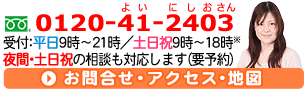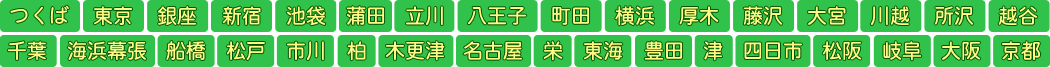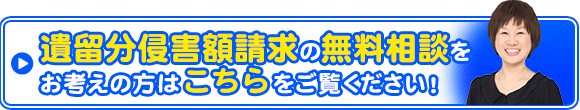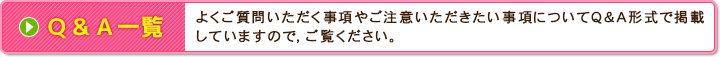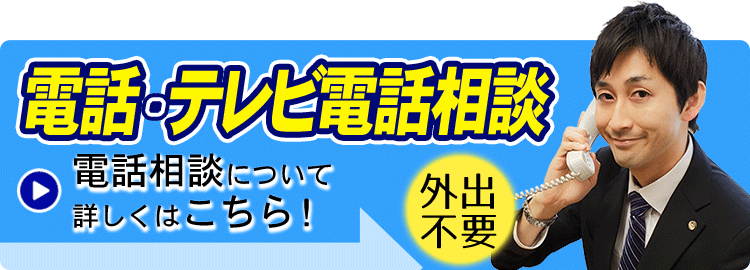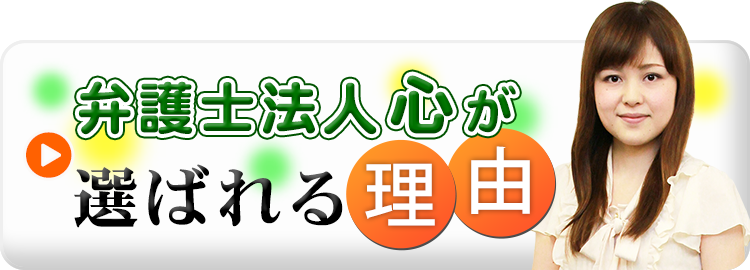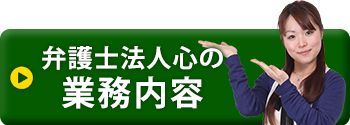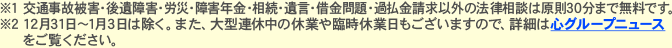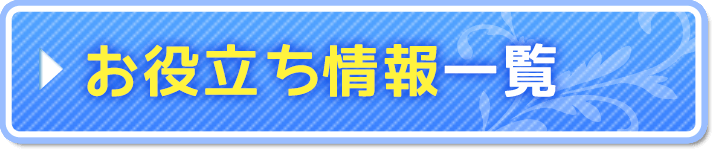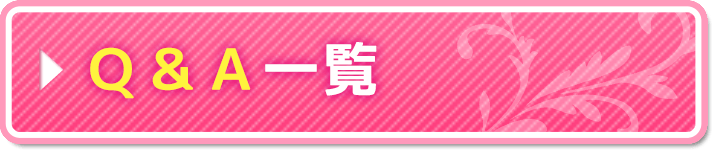特別受益は遺留分の対象となるのか
1 特別受益の一部は遺留分侵害額請求の対象になる
結論から申し上げますと、特別受益のうちの一部は、遺留分侵害額計算の基礎となる被相続人の財産に含められます。
特定の相続人において特別受益が存在することを前提として、その特別受益のうち、原則として相続開始前10年以内になされた贈与を遺留分侵害額計算の基礎に含めることができます。
また、被相続人と生前贈与を受けた相続人の両方において、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与においては、相続開始前10年以内でなくても遺留分侵害額計算の基礎に含まれます。
以下、特別受益に該当する贈与等、および遺留分侵害額請求の対象となる特別受益について詳しく説明します。
2 特別受益に該当する贈与等
特別受益に該当するものには、遺言による相続人への遺贈のほか、婚姻・養子縁組のための生前贈与、生計の資本としての生前贈与があります。
相続人に対する生前贈与であっても、これらに該当しない場合には特別受益にはなりません。
婚姻・養子縁組のための生前贈与には、いわゆる持参金や支度金など、婚姻相手や養親に渡すための金銭が該当します。
生計の資本としての生前贈与には、住宅の購入資金の援助や、事業資金の援助などが該当します。
3 遺留分侵害額請求の対象となる特別受益
2で述べた特別受益のうち、相続開始前(被相続人がお亡くなりになる前)10年以内のものは、原則として遺留分侵害額計算の基礎となる相続財産に含めることができます。
特別受益に該当する生前贈与については、類型的に被相続人も相続人も若い時期に行われるものもあり、相続開始の日より10年以上前に行われることも多いので注意が必要です。
被相続人・相続人両方において、遺留分侵害があることを知りながらした贈与については、相続開始前10年以内という制限なく遺留分侵害額計算の基礎に含めることができますが、当事者双方が遺留分侵害の事実を知っていたということについては、当時の被相続人の財産の状況やその認識等を、間接的な資料でもって証明していく必要があります。
遺留分侵害額請求について|請求の対象や交渉がまとまらない場合の対応 相続放棄を検討中の方