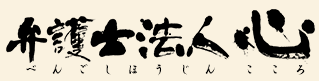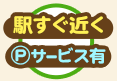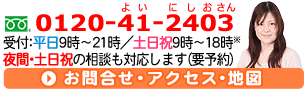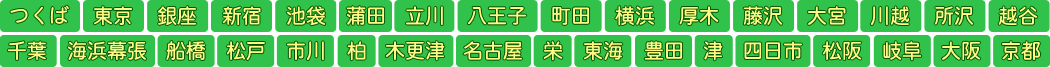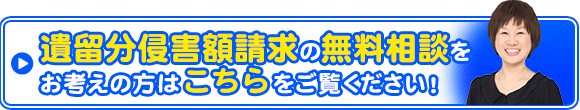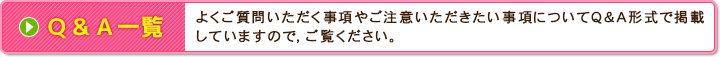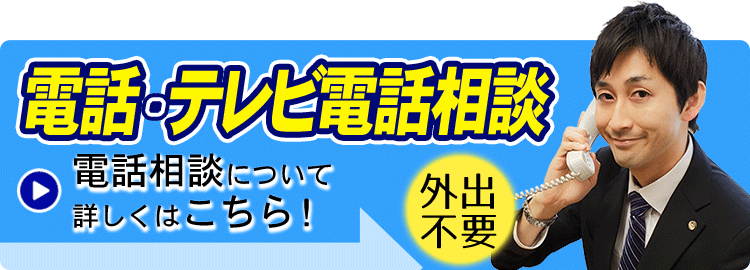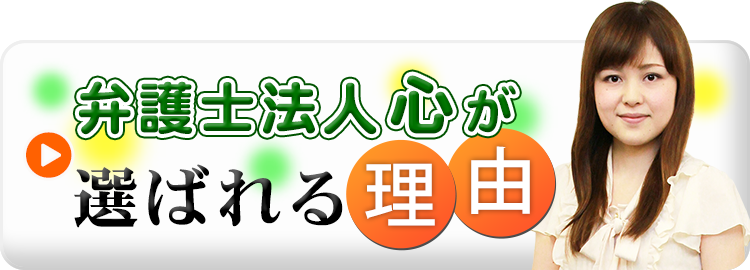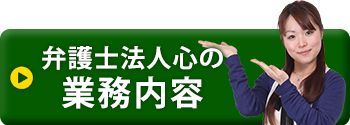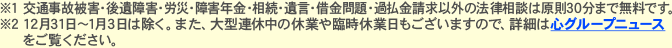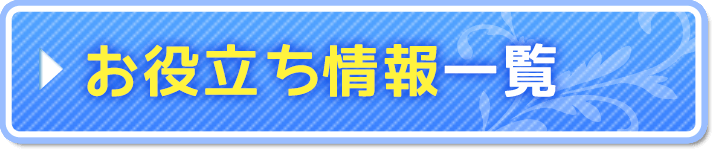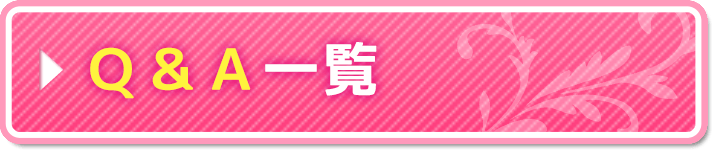遺留分侵害額請求について|請求の対象や交渉がまとまらない場合の対応
1 遺留分について
遺留分とは、「兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている、最低限の遺産の取り分」のことです。
遺留分をもらえる人のことを遺留分権利者と呼びます。
相続人の配偶者や子が該当し、子がいない場合は父母などの直系尊属が該当します。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の遺産に対する割合は民法で次のように定められています(民法1042条)。
直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合:遺産全体の1/3
その他の場合:遺産全体の1/2
この割合に法定相続分を掛けたものが、相続人一人ひとりの遺留分になります。
例えば配偶者と子ども2人が相続人のときは、上記「その他の場合」に当てはまるため、遺留分は配偶者が1/4、子ども2人がそれぞれ1/8ずつとなります。
2 侵害された遺留分は取り戻す権利があります
この遺留分という制度は、遺族の生活保障のためにあるとされています。
被相続人が遺言書をのこしている場合、本人の意思を尊重し、基本的には遺言書の通りに遺産分割します。
しかし、それだけでは被相続人の好き嫌いによって、一部の相続人が全財産を相続して他の相続人は全く相続できない、というようなことも起こりえます。
そこで民法は、遺された相続人の生活を最低限保障する目的で遺留分制度を設けているのです。
このような制度趣旨から、遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」(2019年7月1日の民法改正以前は「遺留分減殺請求」。遺留分制度は、2019年7月1日から大きく改正されています。)を通じて取り返すことができます。
3 遺留分の時効に注意
ただし、この請求権には時効があることに注意が必要です。
遺留分侵害額請求は、相続発生及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間、知らなかったとしても相続開始から10年間以内に行わなくてはなりません。
4 遺留分侵害額請求の対象
遺留分が侵害されるケースとして挙げられるのは、不平等な内容の遺言書による相続・遺贈のほか、贈与もあります(生前贈与・死因贈与)。
生前贈与とは、読んで字のごとく、被相続人が生前に特定の人物に財産を譲渡することです。
死因贈与とは、贈与者が亡くなった時点で効力を生じる贈与のことです。
贈与は時期や受贈者が誰かによって遺留分侵害額請求の対象にできるかどうかが変わります。
被相続人と受贈者の双方が「法定相続人の遺留分を侵害する」ことを知りながら贈与を行った場合には、時期に関係なく遺留分侵害額請求の対象にすることができます。
他方、遺留分を侵害すると知らずに贈与が行われていた場合、贈与を受けたのが法定相続人であれば相続開始前10年間、それ以外の人物であれば相続開始前1年間の生前贈与について、対象にすることができます。
遺留分侵害額請求の請求先となるのは、受贈者・受遺者です。
つまり、たとえば生前贈与で被相続人から財産をたくさんもらった人や、遺言で遺贈を受けた人など、わかりやすく言えば、過度に利益を受けている人です。
次に、遺留分に関して実際にどんな問題が起こりやすいのか、見てみましょう。
5 遺留分をめぐる問題
遺留分をめぐっては、実際に様々なトラブルが発生します。
その例として、2つのケースをご紹介します。
ケースA:被相続人の遺言書通りに遺産分割が進んでいるが、自分の取り分が極端に少ない気がする
ご自身の遺留分が侵害され、これを取り戻したい場合は、すぐに遺留分侵害額請求を行いましょう。
基本的には、以下の手順で対応します。
1.遺言書や被相続人の遺産・相続人調査などをもとに、本当にご自身の遺留分が侵害されているか、されているならどの程度か算出する(実際には、具体的に遺留分を算定できなくても請求できるとされています)。
2.遺留分侵害額請求の相手方に対して内容証明を送り、請求の意思表示をする。
3.実際に交渉を試みる(交渉で解決しない場合、調停や訴訟に進むことも)。
ケースB:他の相続人から「遺留分を侵害しているからお金を返してほしい」といわれてどうすればよいかわからない
まず、遺留分侵害の事実はあるか、時効が完成していないかなどを確認します。
請求に応じなければならないという場合でも、ご自身が本来支払わなければならない額より高い、不当な請求を受けているケースは多いです。
その場合、適正な金額まで減額するよう交渉します。
遺留分問題は多種多様ですが、いずれにせよ弁護士に相談するのが最も安心です。
6 遺留分の交渉がまとまらない場合
遺留分は、完全に利益が対立する分野であり、当事者同士の交渉が決裂しやすいものの一つと言えるでしょう。
もし交渉が決裂してしまった場合、遺留分権利者は、遺留分侵害額の請求調停という手続きと、訴訟という2つの手段をとることができます。
ただし、訴訟は原則として調停を行ってからでないとできないとされています。
⑴ 遺留分侵害額の請求調停
家庭裁判所に申し立て、調停委員会という裁判官と調停委員によって構成される3名の組織に、遺留分に関する争いの解決に向けて話し合いをサポートしてもらうものです。
訴訟とは異なり、あくまで話し合いでの解決を目指す手続きで、比較的利用しやすいのが特徴です。
なお、2019年6月30日までに発生した相続については、遺留分減殺による物件返還請求等の調停を行うことになりますが、調停の性質は同じです。
⑵ 遺留分に関する訴訟
遺留分の請求について、調停を行ってもなお解決しない場合、残された手段は訴訟しかありません。
再び当事者だけでの交渉を行うこともありますが、調停で解決しない事件が交渉で解決することは稀でしょう。
遺留分については、交渉段階から弁護士にご相談いただくのが安全ではありますが、特に訴訟はご自身だけで行うのは難しく、ぜひ弁護士を頼っていただきたい段階です。
7 遺留分問題について弁護士に相談するメリット
弁護士に相談するメリットはたくさんあります。
たとえば、大前提となる遺留分をご自分だけで算出するのは不安も多いかもしれませんが、弁護士が算出することで、より正確を期すことができます。
また、算出から実際の交渉までご自分ひとりの力で行うのは、かなりの労力を要します。
弁護士に一任すれば、その負担から解放されるとともに、心強い味方ができるはずです。
遺留分は、相続のなかでも特に交渉が難しく、ご自分で行うにはストレスの多い問題です。
弁護士という第三者を介してこそ、親族と冷静に話し合うことができます。
8 まずはご相談ください
しかし、「弁護士」というと敷居が高いイメージがあって、相談するのに抵抗のある方も多いでしょう。
ですが、遺留分侵害のような相続問題の場合、親族に自分の力だけで交渉しようとすると、お金のことでなかなか言い出せずに結局うやむやになってしまったり、言っても親族間で発言力のある人にうまく説き伏せられたりしてしまう可能性があります。
被相続人の遺産額によっては本来かなりの額をもらえるはずが、ご自身が考えているよりも大きく損をしているかもしれません。
弁護士と協働することで、話しにくい場面でも強い姿勢で臨むことができます。
どうしても埒があかない場合は調停や訴訟に進む場合もありますが、まずは当事者同士の話し合いで円満に解決できるように交渉を進めていきます。
また、反対に遺留分侵害額請求を「受けた側」の方についても、いきなりのことに困惑しているかもしれませんが、弁護士なら遺留分問題の取り扱いにも慣れているので、冷静に対処できます。
遺留分についてお悩みの方へ 特別受益は遺留分の対象となるのか